論文解析
論文での情報収集でこんな悩みを抱えていませんか?「研究テーマに合う論文がなかなか見つからない…」「新しい発見やアイデアをもたらすような論文に出会えない…」「論文を解釈・分析する時間がない…」。
創薬の基礎研究において、論文から有益な情報を得るのは非常に大事な作業ですが、実際のところ膨大な数の論文から自分が求めている情報にピンポイントで即アクセスするのは、不可能に近いと言わざるを得ません。
こうした論文の情報収集における課題も、AIの技術を活用すれば、大幅な効率化を図ることができます。ここでは、論文検索・解析における課題を整理しつつ、AIを使った解決方法、ソリューションになりえるサービスを紹介します。
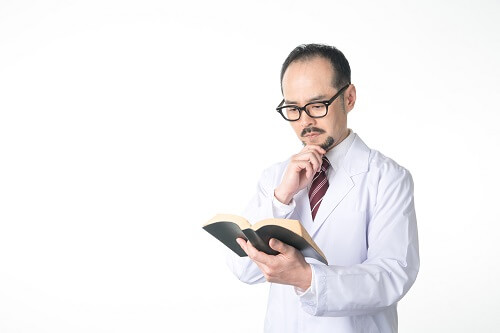
創薬における
論文解析の課題とは?
求めている情報にアクセスしにくい
研究者が頻繁に利用する論文データベースといえば、アメリカのNCBI(国立生物科学情報センター)が運営している生物医学領域論文データベース「PubMed」でしょう。
「PubMed」は世界中の医学系雑誌に掲載された3000万報以上の論文が掲載されているうえ、データベースの更新頻度が非常に高く、リアルタイムで最新の論文情報にアクセスできます。基本的に無料で閲覧できるとあって、製薬企業はもちろん、大学の研究機関などでも利用されています。
これだけの論文が掲載されているのは喜ばしいことではありますが、一方で「求めている情報にアクセスしにくくなっている」という問題も起きています。
例えば、キーワード検索しても既に知っている論文ばかりが表示されてしまったり、キーワードは合致していても研究テーマとの関連性が乏しかったり…。また、本当に関連があるかどうかを調べるには、1つ1つの論文のアブストラクト(論文要旨)をチェックしなければいけないため、作業時間も長くなりがちです。
キーワード検索が大きな障壁の1つに
そもそも創薬という「新しい薬を創る」という文字通り新しい可能性を切り拓く仕事においては、多くの研究者は既知の情報はもとより、新しい気づき・アイデアをもたらす情報を求めています。
しかしながら、PubMedなどの論文データベースでは基本的にはキーワード検索が主流となるため、研究者が「知っている範囲でしか探せない」という弊害が起きています。そうなると、情報の取得範囲は限定的になり、網羅的で客観性のある情報収集は難しくなります。
研究者の知見は創薬において欠かせないものですが、その知見がバイアスとなり、論文情報から「新しい気づき・アイデア」を得られにくくなっているのです。なかでも「キーワード検索」という行為が網羅的な情報探索を難しくしている、大きな障壁の1つになっていると言えるかもしれません。